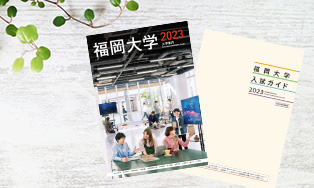社会デザイン工学科

安全で快適に暮らせるまちづくりとそのためのアイテムを想像する、実践力を備えたシビルエンジニアを目指して。

学科のポイント
社会デザイン工学科では、私たちが安全で快適に暮らせるまちづくりとそのためのアイテムを計画、設計、施工、管理するための理論や技術を学習します。
JABEE(日本技術者教育認定機構)認定のカリキュラムでは、構造工学、水工水理学、地盤力学、社会基盤計画学、建設材料学、環境システムの6分野に基礎から応用発展科目までがバランスよく配置されており、興味に合わせてより深く学べるようになっています。
技術や理論だけでなく、景観や環境問題にも配慮できる次代の社会基盤をデザインできる実践力を備えたシビルエンジニアを養成します。
→もっと詳しく(学問の解説・カリキュラムなど)(大学公式サイト)
このような方におすすめ
- 公務員になって社会に貢献したい。
- 安心・安全・快適なまちづくりがしたい。
- 環境保全のための新技術を開発したい。
- 災害から暮らしを守る建設技術者になりたい。
アドミッション・ポリシー(入学者受け入れ方針)
養成する人材像・教育課程の特色
自然環境と調和した生活環境の創造に貢献する人材を養成することを目標としています。この目標に基づき、地球及び地域の環境問題を直視して自然と調和しながら地震や洪水などの災害に強い社会資本整備を行うための建設技術を習得し、強い責任感と倫理感を持って次世代に豊かな生活や文化を継承し続けられる社会のデザインに取り組み、社会で活躍できる人材養成を行います。これを実現するために、建設工学各分野(構造系、水理系、地盤系、計画系、材料・施工系、環境系)を学ぶプロセスでは、基礎的な知識を学ぶ導入科目から、より高度な専門知識まで体系的に学べるようになっています。また、多くの実践的な実験・実習科目も組み込まれており、専門的な知識の習得のみならず実社会で通用する土木技術者を養成するための教育課程となっています。
求める人材像(求める能力)
- 知識・理解
高等学校の教育内容を幅広く学修し、工学を学ぶに十分な基礎学力を有している人 - 技能
社会の問題を自ら調べ倫理的思考に基づいて、自分の意見を論理的に説明することができる人 - 態度・志向性
高度な専門知識と倫理観を身に付けた技術者になることへの夢を持ち、専門知識を社会のために積極的に活用したいと考えている人 - その他の能力・資質
自己研鑽により英語の資格を取得した人や課外活動等で顕著な成績をおさめた人
入学者選抜のねらい
社会デザイン工学科では、建設工学に対する興味を持ち、『人々が、安全かつ快適に暮らせるための社会基盤整備を実現したい』との想いを持った入学者を求めています。
そこで、建設工学を学ぶために必要となる基礎学力はもちろんのこと、建設工学を学ぶ意欲や資質などからも受験者を評価し、多面的・総合的に入学者を選抜する多様な試験を実施します。
実施する入試制度
- 総合型選抜(総合型選抜・アスリート特別選抜)
- 学校推薦型選抜(A方式)
- 一般選抜(系統別日程・前期日程・後期日程・前期日程・共通テスト併用型・共通テスト利用型(Ⅰ期・Ⅱ期))
- その他の入試制度(帰国生徒選抜・社会人選抜(前期日程)・編・転・学士選抜・学部留学生選抜)
募集人員や、他の学部・学科で実施する入試制度は、入試ガイド をご覧ください。
パンフレット・学科紹介動画
学部ガイド・入試ガイド・大学案内など、パンフレットは大学パンフレットからダウンロードできます。
また、受験生のためのライブラリー「FUKUTANA」には、学科紹介動画等も掲載しております。ぜひ、ご覧ください。
ミニ講義ビデオ
![]() 福岡大学教員によるミニ講座や夢ナビWebでの模擬内容の閲覧のほか、講義ビデオや教員からのメッセージビデオを視聴いただけます。
福岡大学教員によるミニ講座や夢ナビWebでの模擬内容の閲覧のほか、講義ビデオや教員からのメッセージビデオを視聴いただけます。
- 全ての道はゴミ問題に通ず
 (工学部 社会デザイン工学科 准教授 鈴木慎也)
(工学部 社会デザイン工学科 准教授 鈴木慎也) - 全学部・学科の一覧を見る