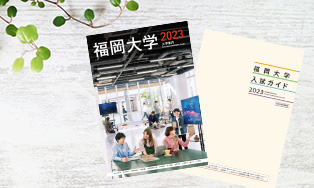法律学科

入門ゼミで楽しく法律に触れ、将来を見すえたコース履修へ。
社会で活躍するためのリーガル・マインドを身に付ける。

学科のポイント
将来の目標に応じて学べる3コース(「法律総合コース」・「公共法務コース」・「総合政策コース」)を設置しています(2016年4月に再編しました)。
それぞれの目標の実現につながる授業を体系的に展開しています。
また、1年次から少人数制のゼミを導入し、4年間を通じて濃密な学びや考察、議論に取り組むことで、社会での活躍の土台となるリーガル・マインドを身に付けていきます。
→もっと詳しく(学問の解説・カリキュラムなど)(大学公式サイト)
このような方におすすめ
- 法律専門職を目指したい。
- 公務員を目指したい。
- 企業で法律知識を生かして活躍したい。
- 政治学を学び、政策に関する知識を身に付けたい。
アドミッション・ポリシー(入学者受け入れ方針)
養成する人材像・教育課程の特色
弁護士などの法律専門家、公務員、企業や地域社会で中心となって活躍する人材を養成することが、われわれの目標です。法律学や政治学を学ぶための基礎を身につけた上で、将来の目標に向けて必要な専門科目を効率的に履修することができるようにするため、三つのコースを用意しています(2年次にコースを選択します)。①法律系資格の取得・法科大学院などの大学院への進学・一般企業への就職などを目指し、基本的な法律科目である憲法・民法・刑法などの六法科目を中心に、法律を総合的に学習する「法律総合コース」、②公務員・公共団体職員・外交官などを目指し、憲法・行政法・国際法など、公法科目を中心に学習する「公共法務コース」、③公務員・政策スタッフ・マスコミ・社会福祉団体職員・NPOなどを目指し、政治系・政策系・福祉系科目を中心に学習する「総合政策コース」があります。
求める人材像(求める能力)
- 知識・理解
高等学校の教育内容を幅広く学修しており、法律学や政治学を学ぶのに十分な基礎学力(読み書きの力を含む)を有している人 - 技能
学んだ知識をもとに、問題解決のあり方を示すことができる人 - 態度・志向性
社会で生じているさまざまな問題を積極的に解決しようとする姿勢や、積極的に社会に貢献しようとする姿勢を持つ人 - その他の能力・資質
英語の資格を取得した人や、スポーツ活動などで顕著な成績をおさめた人
入学者選抜のねらい
法学部での勉強では、広い視野を持ち、さまざまな角度から考えることが必要になります。そのため、法学部では、AO入試、推薦入試、一般入試のほか、特別入試として、帰国子女入試、社会人入試、学部留学生入試、編・転・学士入試などの多様な入試を実施し、さまざまな能力を持つ人材を国内外から広く受け入れています。
実施する入試制度
- 総合型選抜(総合型選抜・アスリート特別選抜)
- 学校推薦型選抜(A方式)
- 一般選抜(系統別日程・前期日程・後期日程・前期日程・共通テスト併用型・共通テスト利用型(Ⅰ期・Ⅱ期))
- その他の入試制度(帰国生徒選抜・社会人選抜(後期日程)・編・転・学士選抜・学部留学生選抜)
募集人員や、他の学部・学科で実施する入試制度は、入試ガイド をご覧ください。
パンフレット
学部ガイド・入試ガイド・大学案内など、パンフレットは大学パンフレットからダウンロードできます。
ミニ講義ビデオ
![]() 福岡大学教員によるミニ講座や夢ナビWebでの模擬内容の閲覧のほか、講義ビデオや教員からのメッセージビデオを視聴いただけます。
福岡大学教員によるミニ講座や夢ナビWebでの模擬内容の閲覧のほか、講義ビデオや教員からのメッセージビデオを視聴いただけます。
- 会社から不当な扱いを受けたとき、労働法に何ができる
 (法学部 准教授 所 浩代)
(法学部 准教授 所 浩代) - 全学部・学科の一覧を見る