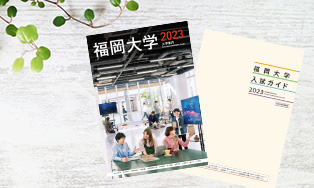薬学科

学部・学科 > 薬学部
基礎的・臨床的な先端医療研究を土台とする6年間一貫教育。医療人として社会から真に信頼される薬剤師となるために。

学科のポイント
医療技術の高度化や創薬につながる科学の進歩、医薬分業の進展などを背景に、薬剤師が担う使命は大きくなり続けています。
これらを踏まえ本学薬学科では、「医薬品の開発や安全使用に関する基礎的・臨床的先端研究の推進をもって、国民の健康と福祉に貢献する」を理念とする6年間一貫教育により、次のような薬剤師を養成します。
- 「チーム医療」の現場で医師や看護師などと協力・活躍できる薬剤師。
- 全人教育(医療人としての幅の広い人間性の醸成のための教育)により、豊かな教養教育を身に付けた薬剤師。
- 医薬品に対する深い専門的知識と医療人としての確固とした倫理観と研究マインドを持った質の高い薬剤師。
- 環境や食品衛生の向上に寄与し、人々の健康維持・増進に貢献しうる薬剤師。
- 臨床マインドを持って医薬品の開発、創薬などに従事する薬剤師。
→もっと詳しく(学問の解説・カリキュラムなど)(大学公式サイト)
このような方におすすめ
- 薬剤師・薬学研究者として医療に貢献したい。
アドミッション・ポリシー(入学者受け入れ方針)
養成する人材像・教育課程の特色
薬学部薬学科は、『医薬品の開発や安全使用に関する基礎的、臨床的先端研究の推進をもって国民の健康と福祉に貢献すること』を教育研究の理念としています。この理念に基づき、『基礎科学の総合を基盤としながら、医療人としての倫理観、使命感そして責任感を十分に理解し、高度な薬学の知識・技能を身につけ、生涯にわたり自己成長できる薬剤師、並びに教育・研究者の養成』を目指しています。このための教育課程は、少人数教育を基本とし、低学年時に基礎的な薬学科目を、高学年時により薬剤師として必要とされる臨床的技能を含めた専門性の高い薬学科目を配置することで、確かな学力・技能の向上に配慮しています。
求める人材像(求める能力)
- 知識・理解
高等学校の教育内容を幅広く学修しており、探究心旺盛で科学に関する素養を有する人 - 技能
患者ならびに医師をはじめとする医療関係者と適切に連携できるコミュニケーション能力を備えている人 - 態度・志向性
思いやり、倫理観、使命感そして強い責任感を備えている人 - その他の能力・資質
医療業界のグローバル化に対応するため英語の資格を取得した人やスポーツや生活習慣を通じて、心身の健康維持・増進を目指す姿勢を持っている人
入学者選抜のねらい
薬学部薬学科は、基礎科学の総合を基盤としながら、将来医療人になるべく倫理観、使命感そして責任感を十分に理解できる人材を国内外から広く受け入れます。そのために、これまでに培われた基礎学力、活動や経験を通じて身につけた能力、技能、学ぶ意欲を、多面的・総合的に評価する多様な入学試験を実施します。
実施する入試制度
- 学校推薦型選抜(A方式)
- 一般選抜(系統別日程・前期日程・後期日程・前期日程・共通テスト併用型・共通テスト利用型(Ⅰ期・Ⅱ期))
- その他の入試制度(帰国生徒選抜・社会人選抜(後期日程)・学部留学生選抜)
募集人員や、他の学部・学科で実施する入試制度は、入試ガイド をご覧ください。
パンフレット・学科紹介動画
学部ガイド・入試ガイド・大学案内など、パンフレットは大学パンフレットからダウンロードできます。
また、受験生のためのライブラリー「FUKUTANA」には、学科紹介動画等も掲載しております。ぜひ、ご覧ください。
ミニ講義ビデオ
![]() 福岡大学教員によるミニ講座や夢ナビWebでの模擬内容の閲覧のほか、講義ビデオや教員からのメッセージビデオを視聴いただけます。
福岡大学教員によるミニ講座や夢ナビWebでの模擬内容の閲覧のほか、講義ビデオや教員からのメッセージビデオを視聴いただけます。
- 災害救護活動の最初に行うこと
 (薬学部 教授 江川 孝)
(薬学部 教授 江川 孝) - 成人T細胞白血病患者を救いたい
 (薬学部 准教授 小迫 知弘)
(薬学部 准教授 小迫 知弘) - 全学部・学科の一覧を見る