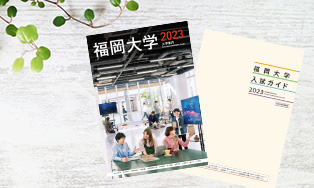歴史学科

一人一人に向き合う細やかな指導。
専門性の高い”考える歴史”に取り組む。

学科のポイント
歴史学科で学ぶのは「考える歴史」です。
日本史であれば古文書を、東洋史であれば漢文の文献を、また西洋史であれば欧文の文献を読み、理解や考察に基づく論文を作成します。
それは専門性の高い学びではありますが、段階的に組まれたカリキュラムや学生一人一人への細やかな指導が4年間を支えます。
また学生参加型の授業や学会との連携など、充実した教育環境がもたらすメリットも多々あります。
卒業後は培った”考える力”を生かして企業への就職はもとより、研究者や博物館学芸員、考古学の専門家を目指し、大学院に進む人も増えています。
→もっと詳しく(学問の解説・カリキュラムなど)(大学公式サイト)
このような方におすすめ
- 単なる暗記ではなく「考える歴史」を学びたい。
- 考古学、日本史、東洋史、西洋史のいずれかに関心がある。
アドミッション・ポリシー(入学者受け入れ方針)
養成する人材像・教育課程の特色
古代以来、文明のクロスロードとして豊かな歴史をはぐくんできた九州の地域性に根ざしつつ、九州から日本史・世界史を見直す地域的な視点と、アジア、ヨーロッパ、アメリカなど世界を見据える国際的な視点とを併せ持つ教育と研究の推進を理念とします。歴史学科では、少人数教育を徹底しておこない、導入教育において大学生としての基本的能力を養い、さらに専門教育では、日本史、東洋史、西洋史、考古学の各分野において高い専門性と複眼的な幅広い視野をもつ人材の養成を目指します。
求める人材像(求める能力)
- 知識・理解
高等学校の教育内容を幅広く学修しており、歴史学を学ぶに十分な基礎学力を有している人 - 技能
問題点を発見し、それを他者に分かりやすく説明することが出来る人 - 態度・志向性
歴史学の高度な専門知識や幅広い教養を生かして社会で活躍したいと考える人 - その他の能力・資質
スポーツなどの課外活動で優秀な成績をおさめた人や英語の資格を取得した人
入学者選抜のねらい
歴史学科は、大学で学んだことを生かした職業で活躍したいと希望する意欲あふれる人材を国内外から広く受け入れます。
そのために、これまでに習得した基礎学力、諸活動や経験を通じて培った能力などを多面的かつ総合的に評価する多様な入学試験を実施します。
実施する入試制度
- 総合型選抜(アスリート特別選抜)
- 学校推薦型選抜(A方式)
- 一般選抜(系統別日程・前期日程・後期日程・前期日程・共通テスト併用型・共通テスト利用型(Ⅰ期・Ⅱ期))
- その他の入試制度(帰国生徒選抜・社会人選抜(前期日程)・編・転・学士選抜・学部留学生選抜)
募集人員や、他の学部・学科で実施する入試制度は、入試ガイド をご覧ください。
パンフレット
学部ガイド・入試ガイド・大学案内など、パンフレットは大学パンフレットからダウンロードできます。
ミニ講義ビデオ
![]() 福岡大学教員によるミニ講座や夢ナビWebでの模擬内容の閲覧のほか、講義ビデオや教員からのメッセージビデオを視聴いただけます。
福岡大学教員によるミニ講座や夢ナビWebでの模擬内容の閲覧のほか、講義ビデオや教員からのメッセージビデオを視聴いただけます。
- なぜ鄭和の艦隊はコロンブスほど有名ではないのか
 (人文学部 歴史学科 東洋史 教授 則松 彰文)
(人文学部 歴史学科 東洋史 教授 則松 彰文) - 全学部・学科の一覧を見る