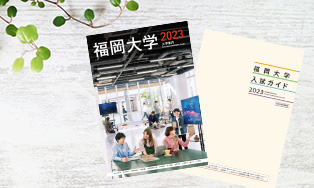看護学科

社会医療に尽くし、人々の健康と幸福に貢献できる創造的な看護人材を目指して、幅広く看護学を学ぶ。

学科のポイント
教育理念
生命の尊厳に基づいた心豊かで総合的な人間教育を基盤として、創造的で国際的・学際的視野に立った論理的・倫理的な看護実践能力を育成し、看護学の発展並びに地域・国際社会に貢献する。
看護学は、自然科学と人間科学を包括し、幅広い教養や見識が必要とされる学際的学問です。そのことを大前提に、福岡大学病院と福岡大学筑紫病院からのサポートをはじめ、恵まれた環境を利用して教育を推進します。地域はもとより国際社会における医療に尽くし、人々の健康・幸福に貢献できる創造的な看護人材を育成します。
→もっと詳しく(学問の解説・カリキュラムなど)(大学公式サイト)
このような方におすすめ
- 人に寄り添い、温かいケアができる看護職を目指したい。
アドミッション・ポリシー(入学者受け入れ方針)
養成する人材像・教育課程の特色
人々の健康を保持増進し、病気を持ちながら生活する人々に寄り添い、その人らしく生きることを支え、さらに地域・国際社会に貢献できる看護専門職者を育てることが私達の目標です。そのために、総合大学としての特徴を生かし、幅広い教養と知識を修得するための科目や、看護の基盤となる人間、健康、環境について多角的に理解する科目、多様な場で看護を実践する能力を身につけるための科目を配置しています。総合大学としての人間教育の特色や専門的な臨地実習施設等の恵まれた環境を活かし、看護実践能力の育成を目指します。また、看護職として幅広い活躍の場が得られるように、選択制で保健師履修コースと養護教諭一種・高等学校教諭一種(看護)の教職課程を設置しています。
求める人材像(求める能力)
- 知識・理解
高等学校の教育内容を幅広く学習しており、看護学を学ぶに十分な基礎学力を有している人 - 技能
自らの視点で物事を順序立てて説明し、他者と良好な人間関係を築くことができる人 - 態度・志向性
人々の健康と生活を支える看護専門職を目指す高い志と倫理観をもち、自ら学び、自己の成長を目指し、挑戦しようとする人 - その他の能力・資質
英語の資格を取得した人や課外活動・ボランティア活動に積極的・継続的に参加し活躍した人
入学者選抜のねらい
看護学科は、学びや諸活動の中で挑戦し続ける意欲あふれる人材や、人とのかかわりを大切にできるさまざまな能力を有する人材を広く受け入れます。
そのために、これまでに培われた基礎学力、活動や経験を通じて身に付けた能力、資質、学ぶ意欲などを、多面的・総合的に評価する多様な入学試験を実施します。
実施する入試制度
- 学校推薦型選抜(A方式)
- 一般選抜(系統別日程・前期日程・前期日程・共通テスト併用型・共通テスト利用型(Ⅰ期・Ⅱ期))
- その他の入試制度(帰国生徒選抜)
募集人員や、他の学部・学科で実施する入試制度は、入試ガイド をご覧ください。
パンフレット・学科紹介動画
学部ガイド・入試ガイド・大学案内など、パンフレットは大学パンフレットからダウンロードできます。
また、受験生のためのライブラリー「FUKUTANA」には、学科紹介動画等も掲載しております。ぜひ、ご覧ください。
ミニ講義ビデオ
![]() 福岡大学教員によるミニ講座や夢ナビWebでの模擬内容の閲覧のほか、講義ビデオや教員からのメッセージビデオを視聴いただけます。
福岡大学教員によるミニ講座や夢ナビWebでの模擬内容の閲覧のほか、講義ビデオや教員からのメッセージビデオを視聴いただけます。
- 老年看護で大切なのは、生きる意欲をいかに引き出すか
 (医学部 看護学科 教授 久木原 博子)
(医学部 看護学科 教授 久木原 博子) - 全学部・学科の一覧を見る